小学4年生で習う都道府県は、覚える数も多く、習ってから短期間で暗記するのはとても大変です。
わが子のクラスでは、都道府県テストで満点はたった2人だったそうで、みなさん苦労して覚えているようでした。
この記事では、わが家で実践した体験をもとに、小学校低学年から遊びの中で都道府県を楽しく覚える方法をご紹介します。
低学年からOK!都道府県の覚え方ポイント
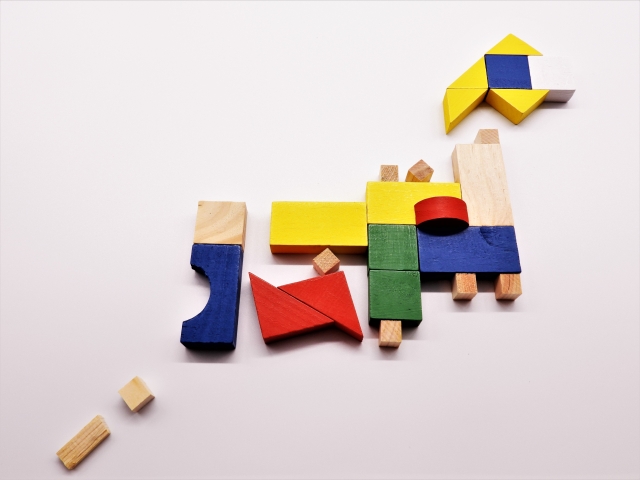
小学4年生の社会科で習う都道府県の県名。
都道府県を全く知らない子供が、いきなり47個も場所と県名を覚えるのは結構大変です。
ちょうど同じ時期に国語の授業でも都道府県の漢字を習うため、県名を漢字で書かないといけないのです。
わが家では子供が小学1年生の頃からパズルやカルタなどを使って都道府県を自然に覚えられるようにしてきました。
ここではその時の体験をもとに、小学校低学年からできる覚え方をいくつかご紹介します。
都道府県を覚える方法4選をご紹介!

✓パズルやポスターで位置を覚える
✓カルタで県名を覚える
✓本で県の特徴を覚える
ひらがなを読めないお子さんは都道府県パズルやポスターから始めましょう。
遊びながら、都道府県の形や位置を自然に覚える事ができます。
ひらがなが読めるようになるなったら、カルタを使って県名を覚えていきます。
本を読めるようになったら、都道府県に関する本を読んで、県の特徴を覚えていくと知識が定着していきます。
わが家で使用した教材も含めて、低学年でも使いやすいものをいくつかご紹介します。
1.都道府県パズル
都道府県パズルは平面タイプと立体タイプがあります。
平面タイプは価格がお手頃でかさばらないというメリットがあり、立体タイプは低学年でも扱いやすい厚みのあるピースになっているというメリットがあります。
また、立体パズルにはプラスチック製と木製がありますが、県の形が細かいところまで再現されています。
平面パズル
学研のパズル 日本列島(学研)
見た目がカラフルで価格がお手頃な学研の日本地図パズル。
パズルピースはリバーシブルになっていて、表には都道府県名と都道府県庁所在地の位置が書かれ、裏には都道府県庁所在地名が書かれています。
パズルボードの表には特産物や世界遺産がイラストで紹介され、底面に主な河川や山地などが紹介されています。壁に貼れるA2サイズの日本地図やおかたづけ用袋もついていて、とても便利です。
るるぶ都道府県がよくわかる日本地図パズル(JTB)
後にご紹介する『るるぶ地図でおぼえる都道府県大百科』がパズルになったものです。
2枚のパズル台紙を組み合わせで遊ぶようになっていて、都道府県の形と名前がわかりやすいシンプルなピースです。
ピースの裏には都道府県庁所在地名、パズル台紙には、おもな山・川・平野などが載っています。パズルの裏面で、都道府県シルエットクイズにもチャレンジできます。
パズルのほかに、地理学習の要点を押さえた「地理学習まとめボード」もついています。
立体パズル
くもんの日本地図パズル(くもん)
小さい子でも遊びやすいプラスチック製の立体パズル。ピースは、カラフルな「基本ピース」と無地の「発展ピース」の2種類があり、習熟度に合わせてステップアップしながら長く遊べます。
パズル以外に、ひらがなシール、都道府県名を隠すめかくしシール、 都道府県名確認地図、地形図、産物・名所の地図、 ピース収納袋2枚が付属していて便利です。
わが家はくもんの世界地図のパズルの方を持っていますが、立体のピースなので、低学年でもつかみやすく、置いたピースがずれにくいので、とても使いやすかったです。

木製パズル 日本地図(学研)
各都道府県の形が細かく再現されており、特産物や名所なども一緒に学べる木製パズルです。 贈り物にも喜ばれます。
「都道府県形覚え表」は語呂合わせで楽しく都道府県の形が覚えられます。 形覚え表を「読み札」にパズルピースを「取り札」にすればかるた遊びもできます。
2.都道府県ポスター
ポスターには壁に貼るタイプとお風呂に貼るタイプがありますが、トイレの壁かお風呂の壁にポスターを貼るのがおすすめです。
子どもが他に気を取られない場所に貼ると、自然に目が向くようになります。お風呂で親と一緒に会話しながら楽しむと効果的です。
家の壁に貼るタイプであれば、パズル、かるた、本などの他教材に付属品として日本地図がついている場合が多いので、そちらを利用しても良いと思います。
小学低学年 学習日本地図(JTB)
水をつけるとお風呂の壁に貼れる、「ユポFGS」紙を使用しており、乾いた場所でも濡れた場所でも使えます。
地方ごとに色分けされており、都道府県の形や位置がわかりやすいです。
各都道府県の特産品をイラストで掲載されており、県庁所在地や全国10位までの山や川、湖の情報もあります。
こたえがでてくる!おふろでスタディ日本地図(パイロット)
都道府県名と都道府県庁所在地がインクで隠されており、お湯をかけて温めると答えが出てくるお風呂用ポスター。
シート4枚を組み合わせて貼って1枚のポスターにするタイプです。
インクが消えるというアイデアが面白く、さすがパイロット社です!名所名産などによる都道府県名当てクイズも一緒に楽しめます。
3.都道府県カルタ
どのカルタにも豊富な情報が載っているため、迷う場合は読み札で読み上げる文章(情報の内容)を基準に選ぶといいと思います。
地形の特徴だったり、特産品だったり、いろいろな読み札がありますので、子供に覚えてもらいたい情報で選んでみましょう。
都道府県かるた(学研)
読み札には、都道府県の県名と地形など特徴が書かれており、その情報をヒントに絵札を取ります。
絵札の裏には、各都道府県の代表的な地理情報や、名産・特産物、世界遺産など、さまざまな情報が掲載されています。
付属のカバーシールを絵札の都道府県名の上に貼りつければ、より高度なかるた遊びができ、絵札の穴にリングを通せば、学習用の暗記カードにもなります。
Amazonアレクサによる読み上げ音声が無料で付いているので、1人で暗記学習をしたり、2人以上でかるた対戦をする事もできます。
かるたの他には、大判日本地図、日本列島白地図も付属しています。
るるぶ都道府県いちばんかるた(JTB)
読み札には、リズミカルな五・七・五 調の読み上げ文があり、県の特徴をヒントに、取り札の県名の頭文字、もしくはイラストを探して取ります。
読み札の裏には都道府県の輪郭図があり、シルエットクイズができます。取り札の裏には情報がぎっしり書かれており、取った県の知識を深掘りできます。
専用のアプリをダウンロードすると、自動読み上げ音声が利用できますが、読み上げ方を選択する事ができます。

かるた以外に日本地図&ゲーム面ポスターが付属しています。

4.都道府県の本
都道府県を紹介した本はたくさん出版されていますが、低学年でも楽しく幅広く学べるものを紹介します。
都道府県の歴史、地形などもっと細かい内容を知りたくなったら、学びたい内容に合わせて他の本も選んでみましょう。
るるぶ地図でよくわかる都道府県大百科
旅行ガイドブックならではの切り口 で都道府県を紹介している都道府県大百科。
地形、名産品、農業、工業、気候といった小学生に必須の知識以外に、ご当地グルメ、温泉、名城、祭りなど、珍しい情報も紹介しており、雑誌を読んでいる感覚で楽しく学習ができます。

にゃんこ大戦争でまなぶ!47都道府県(KADOKAWA)
超人気ゲームの『にゃんこ大戦争』から登場した都道府県の参考書。 全ページオールカラーで漢字にふりがなも付いています。
面白い会話とクイズを楽しみながら、にゃんこたちと一緒に47都道府県を学びます。「自然」「産業」「歴史」「伝統文化」のジャンルごとのポイントをおさえた地図で、「これだけは」という重要ポイントがすっきり学べます。
小学生の社会の予習・復習にはもちろん、家族旅行の時にも役立ちます。
『桃太郎電鉄』で学ぶ47都道府県(学研)
マンガやクイズで楽しく学べる桃太郎電鉄がキャラクターの本。
Nintendo Switch用ゲーム『桃太郎電鉄~昭和 平成 令和も定番! ~』に登場する339の物件駅の特色をオールカラーで紹介しています。
都道府県の地理・歴史、気候、名産、スポーツなどのトピックスを楽しく学べる4コマまんがやクイズ付きです。
都道府県を覚えたら、新聞もおすすめ!
都道府県を学習し、日本に興味が出てきたら、小学生向けの新聞もおすすめです。
わが家では小学2年生から読売KODOMO新聞を読み始めました。
日本各地のニュースが掲載されており、都道府県を知っているとより理解が深まります。
また、都道府県を学習していないお子さんにも、都道府県に興味を持つきっかけになります。
詳しい内容については以下記事でご紹介していますので、ご参照ください。
まとめ
都道府県の覚え方のポイントは、小学校低学年のうちから、遊びの中で自然と覚えていく事です。
都道府県に関する市販教材はいろいろなタイプがありますので、お子さんの年齢や興味に合わせて選んでみてください。
親も一緒に参加すると、楽しく覚える事ができます。




