1歳児にパズルをやらせたいと思っても、薄いパズルはまだつかめない・・・。
こんな時はペグパズルがおすすめです。
パズルに大きなペグがついているので1歳児の発達段階の指先でも簡単につかめます。
ペグパズルはいろいろな種類がありますが、成長に合わせてピースの形を選びましょう。
ここでは、ペグパズルの選ぶポイント、おすすめ品などを解説していますので、是非お子さんと一緒に遊んでみてください。
ペグパズルはいつからできるの?

✔丸ピースは1歳3ヶ月頃から
✔三角、四角ピースは1歳6ヶ月頃から
✔それ以外の形は、三角、四角ができるようになってから
丸ピースは手首を回さずはめられるので、1歳3ヶ月頃から取り組めます。
三角、四角ピースは、はめるのに手首を回す必要があり、形の違いも認識しなければならないため、1歳6ヶ月頃からとなります。
丸、三角、四角の違いがわかると、その他の形も徐々に認識できるようになってきます。
その他の形は丸、三角、四角ができるようになってから取り組むとスムーズに進みます。
我が家の場合は、1歳8ヶ月頃から徐々にできるようになってきました。
※年齢は目安ですので、子供の成長を見ながら取り組んでください。
↓丸、三角、四角のはめ込みパズルについては、こちらの記事をご参照ください。
1歳向けペグパズルのねらい

①指先や手首の動きを発達させる
1歳は指先や手首を動きが活発になってきます。ピースをつまんだり、ピースをはめこむために手首を動かしたりする事で、自分の意思どおりに手を動かす練習をします。
②形の違いを認識する
1歳半頃から、丸、三角、四角などが徐々に認識できるようになってくるため、はめこむ動作を通して、いろいろな形の違いを認識したり、同じ形を見つけたりできるようにします。
1歳向けペグパズルを選ぶポイント
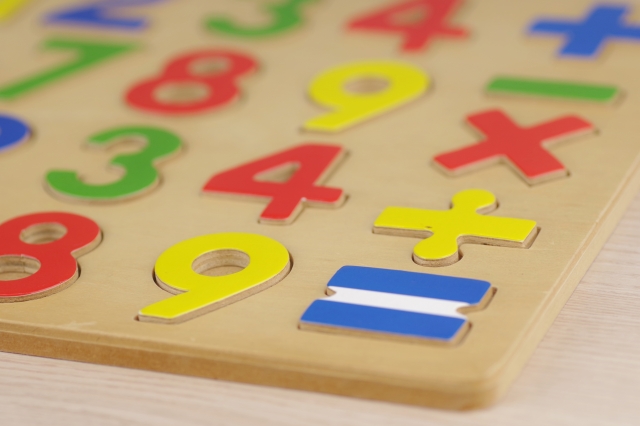
①ピース数は15ピースくらいまで
②各ピースの形の違いがはっきりしているもの
①ピース数は15ピースくらいまで

各メーカーが出しているペグパズルのピース数は、5ピース、8ピース前後、15ピース前後に分けられますが、丸、三角、四角ピースができるようになっていたら、8〜15ピースくらいがいいと思います。
もちろん、5ピースくらいから始めてもいいのですが、早い子供だと1か月くらいでできてしまい、使う期間が短かったという事になるかもしれません。
8~15ピースで多いと感じた時は、最初から全部出さずに5ピースだけ与えるなど工夫をすれば、長く使う事ができます。
②各ピースの形の違いがはっきりしているもの

動物や乗り物などいろいろな種類がありますが、絵柄の周りを大きめに切り取ったピースだと、どのピースも同じような形になっているものがあります。
なるべくピースの形の違いがはっきりしていて、形のバリエーションが多いものを選ぶといいです。
1歳におすすめのペグパズル6選
ペグパズルには、はめる穴にピースと同じ絵柄が描かれているものがあります。
パズルで形合わせをしたい場合は、絵が邪魔にならない無地の方がいいです。
5ピースのペグパズル
1.ゴルネスト&キーゼル リフトアウトパズル(マイジャーニー)
子供の大好きな乗り物が絵柄になった木製パズル。
各ピースの形の違いもはっきりしていて見分けやすいです。
他には農場をテーマにした5ピースのパズルもあります。
2.セレクタ グライフパズル(動物)
やさしい動物の絵柄が特徴の木製パズル。
動物だと普通は絵柄が複雑になりますが、各ピースの形の違いがはっきりしていて、大きめな作りなので、とても扱いやすいです。
7~8ピースのペグパズル
3.ゴルネスト&キーゼル リフトアウトパズル(コンストラクションカー)
はたらく乗り物が絵柄になった7ピースの木製パズル。
各ピースの大きさや形が違っていて、わかりやすいです。
4.ボーネルンド ピックアップパズル(動物園)
絵柄が少し複雑な動物の8ピースの木製パズル。
ピースだけ見比べると形の違いがわかりづらいのですが、はめる穴に動物の影が描かれているので、ピースの動物の形と影の形を合わせられるように工夫されています。
14~15ピースのペグパズル
5.ボーネルンド ピックアップパズル(バラエティー)
日常生活でよく目にするものを絵柄にした14ピースの木製パズル。
「おひさま」、「とけい」、「ボール」は丸い形になっていますが、それぞれの大きさが異なっているため、大きさの違いも学べます。
6.グーラ ピックアップパズル(バラエティー)
こちらも日常生活でよく見るものを絵柄とした15ピースの木製パズル。
それぞれのピースの違いがはっきりしていて、形のバリエーションが多いです。はめる部分が赤く着色されているので形が見やすいです。
我が家ではこれを使いました。後ほど遊んだ様子をご紹介しています。
ペグパズルはレンタルもできる!

ペグパズルは購入すると1個あたり数千円かかりますが、定額レンタルサービスを利用すると、同じような価格で1か月あたり5~6個のおもちゃがレンタルできます。
わが家でも定額制レンタルサービスの「トイサブ」を利用していますが、おもちゃ
1個当たりに計算すると、月額600円程度で利用しています。
ペグパズル以外にもいろいろなおもちゃを一緒にレンタルできるので、とてもおトクです。

レンタルするおもちゃはプランナーさんが最適なものを選んでくれますし、自分でリクエストする事もできます。
ご興味のある方はぜひお試しください!
↓トイサブのサービスや特徴についてはこちらでくわしくご紹介しています。
ペグパズルの遊び方(1歳児編)

初めての取り組む場合は、以下の手順で親がゆっくりとお手本を見せながら遊びます。
①ピースを全部はずしてから、一つのピースを手にとります。
②ペグパズルの穴から同じ形を探す様子を見せます。
③同じ形の穴が見つかったら、ピースを穴の形に合うように手首を回してはめます。
④子供にやってみたいか尋ね、やりたい場合はやらせます。興味が無さそうだったら、また今度にします。
ピースが多すぎてうまくできない場合は、形の違いがはっきりしたピースを3~5つほど選んで取り組み、徐々に数を増やしていくといいです。
丸、三角、四角のピースがある場合は、最初の3~5ピースに入れておくと取り組みやすいです。
1歳児がペグパズルで遊んだ様子
我が家では、丸、三角、四角のペグパズルができるようになった1歳8ヶ月から取り組み始めました。
グーラのパズルを使いましたが、穴のところが赤く着色されているので、ぱっと見てわかりやすいです。

やはり丸ピースは何の迷いもなくすぐにできます。(他のはまっているピースは親が見本を見せるためにはめたものです。)

次に、バナナ、魚、ラケット、傘など、形に特徴のあるピースがわかりやすいようで、はめていきます。ただ、魚とラケットは形が似ているため、わかりづらいようで、ラケットを魚の穴にはめようとしたりしています。



形の特徴がはっきりしていないものは、区別が難しいようでまだはめようとしません。

全体の50%くらいのピースをはめる事ができるようになりました。
1歳9ヶ月になると、星と花を除いて、ほとんどのピースをはめる事ができるようになりました。
星と花は形が非対称なので、はめる時に何度も手首を回さないといけなくて、難しいようです。
実感!ペグパズルの効果

✔手首をうまく回せるようになった。
✔形の違いを認識し、物をよく観察できるようになった。
1歳児は手首がうまく回せない事がありますが、ピースをはめようと何度も手首を動かすことで、うまく回せるようになっていきました。
また、パズルで遊び始めた当初は形の違いを区別できない事がありましたが、遊ぶうちに形をよく観察するようになり、細かい形の違いが認識できるようになりました。
まとめ
ペグパズルをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
かわいい絵柄のパズルだと子供も楽しく遊ぶ事ができますので、ぜひお子さんにぴったりのペグパズルを選んでみてください。
ペグパズルができるようになったら、複数のピースで1枚の絵を完成させる知育パズルに取り組んでみましょう。
知育パズルについては、こちらをご参照ください。
ペグパズルと並行して、型はめパズルに取り組むのもおすすめです。








